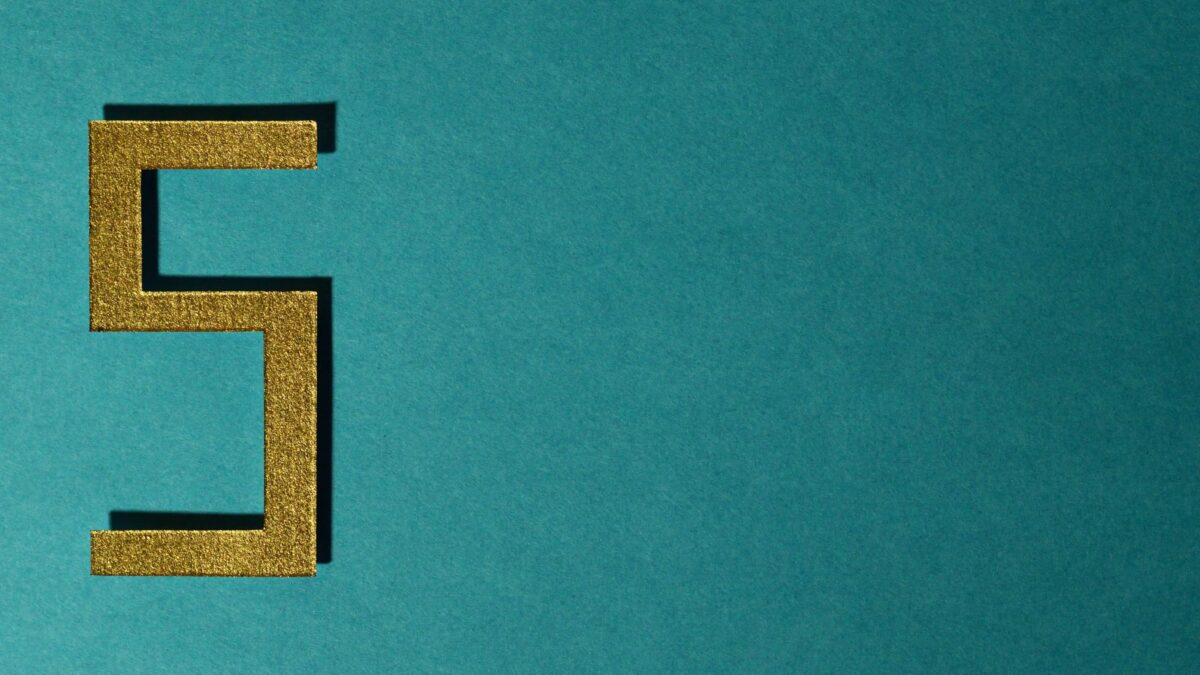── 登記・火災保険・通電・郵便物・鍵管理を「その日から」始めよ
◆ はじめに|「空き家になった瞬間」から、時計は動き出す
親が施設に入った、転勤になった、相続した実家が空いた──
こうした「空き家化」の瞬間、気持ちもバタつくために多くの人が手続きや管理を後回しにしてしまいます。
でも実際には、空き家になった“その瞬間”から劣化やトラブルは始まっているのです。
ここでは、不動産屋でも自治体でもなかなか教えてくれない「すぐにやるべき5つのこと」を生活者視点で解説します。
①「登記簿の名義」を即確認する(相続放置はトラブルの元)
空き家になった時点でまずやるべきは、誰の名義になっているかの確認です。
- 被相続人のままのケース:早期に相続登記の準備を
- 共有名義になっている:相続人間での話し合いを速やかに開始
- 登記簿を法務局で取得(500円程度)or オンラインで閲覧可能
📝 POINT:2024年4月から相続登記は義務化(3年以内)されています。
②「火災保険」を空き家仕様に見直す(対象外になるケースも)
空き家になった住宅は、火災保険の補償対象から外れることがあります。
- 現在の保険契約が「居住用」のままでは補償外になる可能性
- 火事や漏水、台風被害でも“対象外”になってしまうリスク
- 必ず保険会社に「空き家状態になった」と連絡を入れ、
→ 空き家用特約付き火災保険に切り替えましょう
📝 POINT:地震保険も引き続き適用できるか確認を。
③ 「電気・水道・ガス」は止めない/最小限で維持が基本
多くの人が「空き家だから全部止めよう」と考えがちですが、
実際には通電・通水は最小限残したほうが安全です。
- 電気はブレーカーOFFにするが、契約自体は継続(点検や照明に必要)
- 水道は凍結・破損防止のため、定期的な通水が必要(封水対策)
- ガスは原則止めてOKだが、温水洗浄便座や給湯器の凍結対策が必要な地域は注意
📝 POINT:設備が壊れると修理費が大きいため、完全停止は慎重に判断。
④「郵便物」が来なくなると“人がいない”とバレる
空き家で最も見落とされるのが郵便物の管理です。
- 郵便ポストにチラシやDMが溜まる=空き家バレの最大要因
- 郵便局の転送サービスを使って自宅宛に届けてもらう
- 定期的に巡回する家族や管理者が、ポスト清掃と確認をルーティン化
📝 POINT:ダイレクトメール対策として「受取拒否ハンコ」も活用を。
⑤「鍵管理」は家族内で“誰が持っているか”を明確にする
地味にトラブルが起きやすいのが、鍵の所在管理です。
- 相続人の誰かが勝手に入っていた/鍵を失くしていた等の混乱が多発
- 管理する責任者を1人決め、鍵の所在・複製状況をリスト化
- スマートロック等を導入することで、入退室の履歴管理も可能に
📝 POINT:鍵のコピーが第三者に渡っている場合は、鍵交換を検討しましょう。
◆ まとめ|「空き家になった日」が、全ての始まり
空き家トラブルの多くは、“初期対応の抜け”から始まります。
「後でやろう」は、
→ 配管腐食
→ 雨漏り
→ ゴミ屋敷化
→ ご近所トラブル
→ 相続人間の争い
などの連鎖につながる可能性も。
空き家化したその日こそ、一番重要なスタートライン。
✅ 名義確認
✅ 火災保険
✅ 通電・通水
✅ 郵便物管理
✅ 鍵の所在明確化
この5つを“その日のうちに着手”することで、
今後の管理・活用・売却・相続のすべてがスムーズになります。
🎁 LINE登録特典:「空き家になった瞬間にやるべき5つの行動」チェックシート(PDF)
→ 一枚で確認できる“即行動リスト”を無料配布中
\今すぐ受け取りたい方はこちら/ 【LINEで無料登録】